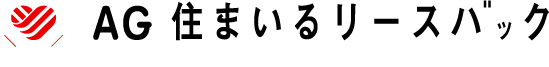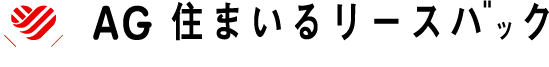リースバックとは、ご所有の不動産を売却しても、
新たな所有者との賃貸契約を結ぶことで、
賃料を支払いながら引き続きその不動産に
住み続けることができます。
また、将来的に
買い戻しができる点も魅力のシステムです。
リースバック契約後のオーナーチェンジで何が起こる?よくあるトラブルや対策を解説
更新日:2025.03.25

リースバックとは、リースバック事業者に自宅を売却したあと、家賃を支払うことで同じ家に住み続けられる仕組みです。売買契約後、新たに住宅の所有者となったリースバック事業者と賃貸借契約を交わし、家賃を支払って暮らします。
リースバック契約後に賃貸生活を続けるなかで、住宅の所有権がリースバック事業者から第三者に移転する場合もあります。この所有権の移転は「オーナーチェンジ」と呼ばれますが、リースバック契約でオーナーチェンジの影響を気にする方もいるでしょう。
本記事では、リースバック契約後にオーナーチェンジが起こった際に、起こりうる事態やトラブル時の対策などを解説します。
リースバックをご検討の方へ
もくじ
リースバック契約の「オーナーチェンジ」とは?
オーナーチェンジとは、賃貸物件の所有者がその住宅に入居者がいる状態で、第三者に売却することです。リースバックも、賃貸物件として暮らす住宅の所有権はリースバック事業者にあるため、オーナーチェンジが起こる可能性があります。
そこで、リースバック契約におけるオーナーチェンジとはどのような状態で居住者にはどのような影響があるのか、わかりやすく解説します。
一般的な賃貸物件でのオーナーチェンジとの違い
賃貸物件でオーナーチェンジがあっても、オーナーには物件の居住者への通知義務がありません。
賃貸借契約の内容に変更がなければ、オーナーチェンジは居住者に事後報告されるのが一般的です。オーナーチェンジにともなって、所有者(家主)と連絡先、家賃の振込先などが変更となる場合、変更事項が通知されるだけで終わるケースが多い傾向です。
一般的な賃貸物件と同様、リースバックで賃貸中の物件も、オーナーチェンジを居住者へ事前通知する義務はありません。そのため、知らないうちに、リースバック事業者から第三者へ所有権が移転している可能性があります。
ただし、一般的な賃貸物件にせよリースバックで賃貸中の物件にせよ、オーナーチェンジがあっても、原則としてすでに結ばれている賃貸借契約が新しいオーナーへ引き継がれます。
リースバック契約後にオーナーチェンジした際の影響
先述のとおり、オーナーチェンジによって住宅の所有権が第三者に移っても、賃貸借契約の内容は原則として引き継がれます。そのため、リースバックでオーナーチェンジがあっても、物件の居住者には大きな影響はないでしょう。
しかし、オーナーチェンジした時点では同じ内容で引き継がれた契約も、新しいオーナーの意向によって変更される可能性もあります。
後々期待していた生活を送れなくなるなど、影響が出る場合も考えられます。
リースバック契約後にオーナーチェンジが起こる理由
リースバック契約後にオーナーチェンジが起こる際には、おもに次のような理由が考えられます。
- リースバック事業者が、家賃収入より物件売却の方が収益面でメリットが大きいと判断したケース
- リースバック事業者の経営悪化により、会社の資産整理の一環で売却されたケース
- リースバック事業者が経営不振により倒産し、物件を手放したケース
また、定期借家契約の場合、リースバックの契約に際して、契約満了後の再契約に同意したあとでオーナーチェンジとなり、再契約できない可能性もあるでしょう。
リースバック契約後のオーナーチェンジで考えられるトラブル

リースバック契約でオーナーチェンジがあった際、通常、契約変更もなく居住者への影響はさほどないと考えられます。しかし、オーナーチェンジがトラブルにつながる可能性もあるでしょう。
そこで、リースバック契約後のオーナーチェンジで想定されるトラブルを紹介します。
事例①新しいオーナーと連絡が取れない
オーナーチェンジしても居住者へ事前通知されない可能性は高く、通常、家賃の振込先などの変更点とともに事後通知されます。
この際、家賃の振込先変更を確認できても、新しいオーナーに関する情報は通知されないケースがあります。
所有権を持たない居住者は、リースバック物件の修繕やリフォームを自由に決める権利がありません。たとえばオーナーに設備の故障を相談したくても、連絡先がわからずいつまでも修繕できないなど、必要な対応が遅れてしまうケースも考えられます。
事例②家賃の値上げや立ち退きを要求される
オーナーチェンジをしても、一般的に賃貸借契約はそれまでの内容で引き継がれます。
しかし、契約満了のタイミングなどで、家賃の値上げや契約更新の拒否、物件からの退去などを、新しいオーナーから求められる可能性もあります。
リースバック契約をした時点では、リースバック事業者と綿密に話し合い、納得できる将来設計を描けていたとしても、思い描いていた暮らしを継続できなくなる場合もあるでしょう。
事例③住宅の買戻しができなくなる
リースバックにおいて、住宅の買戻しの可能性を残せる点は、一般的な不動産売買にはないメリットのひとつです。リースバックを一時的な資金の準備として活用して、やがては自宅を買戻したいと考える方もいるでしょう。
しかし、住宅の買戻しは、法的に保証された権利ではなく、契約したリースバック事業者との約束です。当初の契約では約束されていたとしても、オーナーチェンジにより、買戻しの条件を反故にされる可能性もゼロではありません。
リースバックのオーナーチェンジに備えたトラブル対策
リースバック契約後にオーナーチェンジがあっても、トラブルなく希望どおりの暮らしを実現するために、知っておきたい対策を4つ紹介します。
普通賃貸借契約を選択する
オーナーチェンジで契約内容を変更されないように、普通借家契約を結んでおくのがおすすめです。
普通借家契約にしておくと、原則として契約書どおりの家賃で希望する期間住み続けられます。もし契約更新時に家賃の値上げや立ち退き交渉があったとしても、オーナー側に正当な理由がなければ、居住者には拒否する権利があります。
オーナーチェンジをしても契約内容は原則として引き継がれるため、ご自身の希望をできるだけ細かく契約書に明文化しておくと安心です。
一方、賃貸借の期間に定めがある定期借家契約にすると、オーナー側の事情で再契約を拒否される可能性があります。
オーナーチェンジの際の条項を契約書で定めておく
とくに売却後の自宅に長く住み続ける予定であれば、オーナーチェンジを想定した条項を契約書に記載しておくと安心です。
オーナーチェンジに備えた条項の一例
- オーナーチェンジの際は所有権が移転する前に通知する
- 新しいオーナーによって契約内容は変更されないことを保証する
- 住宅の所有権が移転しても、退去を求められないことを保証する
リースバック事業者と口頭で確認し合うだけではなく、契約書に記載してもらえば、オーナーチェンジへの備えとなります。
オーナーと良好な関係を保つ
事前の相談や通知のない、急なオーナーチェンジによって不都合が起きないように、リースバック事業者とは日頃から良好な関係を保ちましょう。ご自身の希望、生活での困りごとや不安をこまめに相談するなど、日常的に連絡を取り合う関係作りが大切です。
良好な関係があれば、リースバック事業者から事前にオーナーチェンジに関する連絡や相談をしてもらえる可能性が高まります。
信頼できるリースバック事業者と契約する
リースバック事業者がオーナーチェンジを選ぶ理由のひとつは、事業の経営悪化や倒産です。オーナーチェンジを避けられない事情が原因で所有権が第三者に移ると、その後の暮らしに不安を感じるでしょう。
こうしたリスクを回避するためにも、経営の安定した、信頼できるリースバック事業者との契約が大切です。
リースバックを検討する際は、複数の業者から見積りをとったり、業者の経営状態や過去の実績を確認したりするなどして、企業としての信頼度を測りましょう。
リースバック物件に長く住み続けたい場合は事業者選びが大切
リースバックは、自宅の売却代金を得ながら、同じ住宅に賃貸物件として住み続けられる仕組みです。
リースバック事業者の事情が変わると、第三者へ所有権を譲渡されるオーナーチェンジが起こる可能性もあります。しかし、オーナーが変わっても、賃貸借契約の内容は原則として引き継がれるため、居住者の暮らしには大きく影響しないでしょう。
ただし、新しいオーナーの意向によっては、家賃の値上げや契約更新の拒否、急な退去など、予期しなかった要求をされる可能性もあります。万が一実際にトラブルにあった際は、安易に応じず速やかに専門家に相談しましょう。
また、事前の対策としてリースバック契約後のオーナーチェンジで困らないようにするには、ご自身の希望に合った契約内容にするとともに、信頼できるリースバック事業者の選択が重要です。
AG住まいるリースバックは東証プライム上場のアイフルのグループ会社で、長いご契約期間中も安心してお付き合いいただけます。将来の買戻しにも対応するなど、お客様のご希望に柔軟に対応し、納得のいくご契約をサポートします。
自宅の査定額やリースバック契約後の不安など、リースバックにまつわるご相談は無料でお受けしていますので、ぜひ一度ご利用ください。
-
![監修者]()
-
- 監修者:竹国 弘城
-
- プロフィール:
- RAPPORT Consulting Office(ラポール・コンサルティング・オフィス)代表
名古屋大学工学部機械・航空工学科卒業。証券会社、生損保代理店での勤務を経て、ファイナンシャルプランナーとして独立。お金に関する相談や記事の執筆・監修を通じ、自身のお金の問題について自ら考え、行動できるようになってもらうための活動を行う。 - 資格情報:
- 1級ファイナンシャルプランニング技能士、CFP®、宅地建物取引士